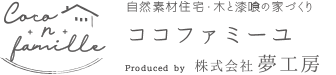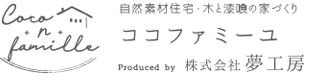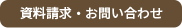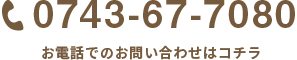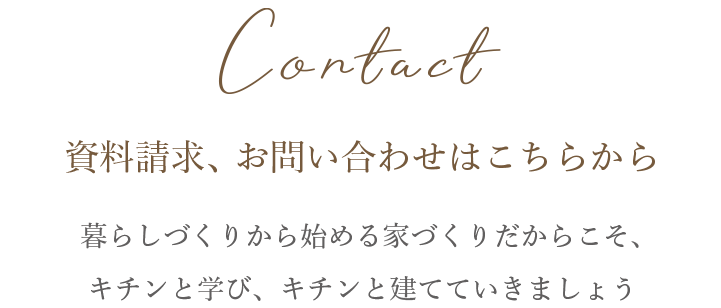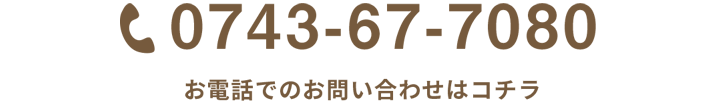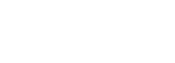自然素材を使った健康的で快適な住まいづくりを行う「ココファミーユ|夢工房」のスタッフです。
私たち親にとって「家」は、日々の暮らしの拠点であり、安らぎの場所。でも、子どもたちにとっては、きっともっと大きな意味を持つ、特別な世界なのでしょう。
ふと気づけば、ほっといたら消えてしまいそうだったか細い泣き声は、今や「もっと上手にできたはずだ」と自分を許せず、悔しさに顔を歪める力強いものに変わっていました。その姿に、頼もしさすら感じます。
親の知らない知識を得意げに語る横顔に、思わず「カッコいいな!」と感心したり。ほんの少しの寂しさと、それを遥かに上回る感謝の気持ちで胸がいっぱいになったり。日々成長する子どもたちの姿は、私たちにたくさんの感情をくれます。
そんな子育ての道の途中、ふと立ち止まって考えるのです。
「子どもにとって、この家はどんな場所だったのだろう?」
「住まいを通して、もっと何かしてあげられることがあったのではないか?」と。
今回は、そんな親心を胸に、めまぐるしく成長する子どもたちの目線で、「家」という存在がどのように変化していくのかを、一緒に考えてみたいと思います。
【幼児期】家 = 世界のすべて。
生まれたばかりの赤ちゃんにとって、世界は「抱っこしてくれる腕の中」。それが少しずつ広がり、幼児期の子どもにとって「家」は世界のすべてになります。
そしてハイハイやよちよち歩きで探検するリビングは、毎日が新しい発見に満ちた大冒険の舞台です。美味しい匂いと音が生まれるダイニングやキッチンは、五感を刺激する不思議で魅力的な空間に映ります。キッチン内に入ろうとする好奇心を抑えられず何度も侵入を試みますよね。
対的な安全地帯は親のそば。その安心感があるからこそ、子どもは家の隅々まで冒険できるのです。
この頃の家は、物理的な建物というより安心そのものです。
そして、その「安心」は、情緒的な面だけではありません。体温調節がまだ苦手なこの時期、家の「性能」もまた、子どもの健やかな成長を支える重要な要素になります。
冬の寒い日、性能の低い家では、お風呂上がりは時間との戦い。震える我が子を風邪ひかせまいと、寒い脱衣所から急いでリビングへ運び、服を着せ、髪を乾かす。自分のことは後回しで、髪が濡れたままだったあの必死な姿。言葉は分からなくても、その必死な愛情は、きっと子どもにも伝わっていたことでしょう。
良い性能の家では必死な姿を見せず、風邪もひかせることはなかったでしょう。
【小学校低学年】家 = 冒険の「基地」。外の世界と自分をつなぐ場所
小学校に上がると、子どもの世界は一気に広がります。学校、友達、通学路。家の外にたくさんの「初めて」が待つ中で、「家」の役割も変化していきます。
「ただいま!」が響く安息地: 外での緊張を解き、ありのままの自分に戻れる場所。家は心のエネルギーを充電する**「安全基地」になります。
友達を呼ぶ、初めての社交場: 「うちに遊びに来ない?」——。家は子ども自身の交友関係が生まれる舞台となり、公園や駄菓子屋といった「土地柄」も、彼らの世界を彩ります。
「好き」が詰まった宝箱: 「自分の机」や「自分のスペース」が特別な意味を持ち始め、大切なもので満たされるようになります。
この時期の家は、外の世界へ冒険に出るための「ベースキャンプ」。傷を癒し、また明日へ飛び立つ元気をくれる場所なのです。
【小学校高学年】家 =「個室」と「リビング」を両立する、心の滑走路
心も体も大人へと近づく高学年。親や友達との関係が深まるこの時期、「家」はさらに多面的な意味を持ち始めます。
扉一枚のプライベート空間: 「一人にしてほしい」という気持ちが芽生え、自分の部屋が「聖域(サンクチュアリ)」になります。誰にも干渉されずに自分だけの世界に浸る時間は、自立に向けた大切な心の成長です。
心地よい距離感を探る場所: 家族と過ごす時間と、一人でいたい時間のバランスを、子ども自身が無意識に探し始めます。それは少し寂しくもありますが、自分という軸を築き始めた証拠です。
社会とつながる窓口: 行動範囲が広がり、家は様々な場所へ出発するための「ハブ」となります。会話も、より広い世界へと関心が向かっていきます。
だからこそ、新たな課題も生まれます。
個室にこもりがちになる時期だからこそ、「リビングの居心地の良さ」が、これまで以上に重要になるのではないでしょうか。
つい自分の部屋に籠ってしまう。でも、リビングに行けば何となく落ち着くし、楽しい。そう思える空間があれば、自然と家族の前に顔を出す時間が増え、学校での悩みなど、子どもの些細な変化に気づくきっかけも生まれるはずです。
尊重すべきプライベート空間と、家族が集う心地よいパブリックスペース。その両立が、この時期の住まいづくりのテーマなのかもしれません。
家は、子どもとともに育つ「幸せの器」
もっと広い部屋を、もっと素敵な子ども部屋を、と考えてしまうかもしれません。ですが、この問いの本当の答えは、間取りやインテリアの中だけにあるのではないのでしょう。
家とは、子どもとともに成長していく「幸せの器」のようなものではないかと思うのです。
その器に注がれるのは、日々の「おはよう」や「おかえり」の声。悔し涙を受け止めた時の、親の温かい腕。他愛ないことで家族みんなで笑い転げた、あの日の記憶。そして、「あなたのことが世界で一番大切だ」という、変わらない愛情です。
それを言葉以外でも伝える。
その機会を家が増やすことができる。
物理的な家という土台の上に、家族の時間、愛情、たくさんの思い出を重ねていくこと。その器を大切に、豊かに育んでいくことこそ、私たち親にできることなのかもしれません。
さぁ、これからも、子どもが成長し、親もともに育つ「幸せの器」でありましょう。 家が家族のためにできることは、きっと、まだまだたくさんあるはずです。